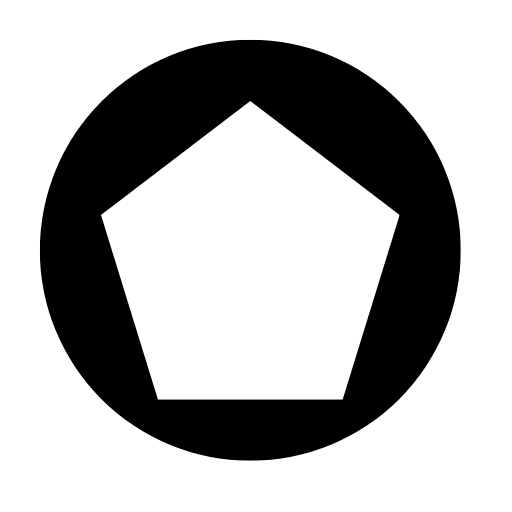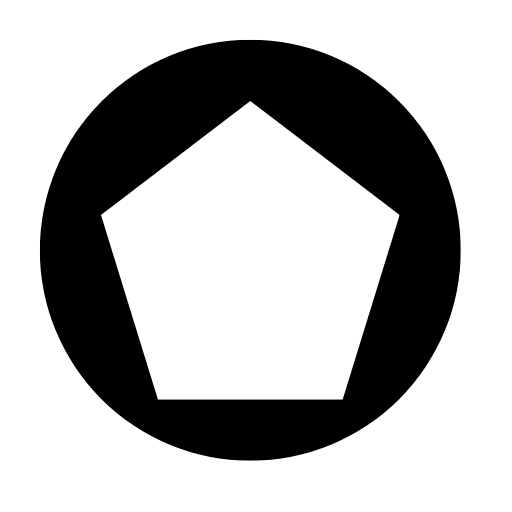障害福祉制度の根拠法と変遷
障害福祉事業の根拠となる法律は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別改正法)などです。
以下法律の変遷となります。
2005年「障害者自立支援法」施行
- 障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化
- 障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現在は「障害支援区分」)が導入
- 国が費用の2分の1を義務的に負担する仕組みや、サービス量に応じた定率の利用者負担(応益負担)が導入 (その後利用者負担については軽減策が講じられる)
2010年「障害者自立支援法」改正
- 利用者負担が抜本的に見直され、これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、負担能力に応じたもの(応能負担)へ
2012年「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」
2013年「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」へ
- 障害者の範囲に難病等が追加
- 障害者に対する支援の拡充などの改正
2016年「障害者総合支援法」改正
- 障害者自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実
- 高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し
- 障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充
2016年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」施行
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの概要
障害福祉事業は、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に大別されます。「地域生活支援事業」は市町村等が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。
「障害福祉サービス」には、17種類のサービスがあり、訪問系、日中活動系、施設系、居住支援系、訓練系・就労系に分けることができます。これらのサービスを利用したときに、かかった費用の9割が「自立支援給付」として支給され、本人の負担は1割となります。自立支援給付は、日常生活における課題のサポートを目的とした「介護給付」と、自立や就労を目的とした「訓練等給付」のいずれかに位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
訪問系(介護給付)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
日中活動系(介護給付)
- 短期入所
- 療養介護
- 生活介護
施設系(介護給付)
- 施設入所支援
居住支援系(訓練等給付)
- 自立生活援助
- 共同生活援助
訓練系・就労系(訓練等給付)
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 就労定着支援
児童福祉制度の根拠法と変遷
児童福祉制度は、児童福祉法を基本として、保育子育て支援施策、ひとり親家庭支援施策、社会的擁護施策、児童虐待対策、障害児支援支援、健全育成、母子保健対策等、非行・情緒障害児施策などの施策が、様々な行政機関や施設、専門職の働きや実践によって推進されています。
障害福祉事業のうち、18歳以下を対象としたサービスについては児童福祉法によって規定されています。
1947年「児童福祉法」制定
2012年「改正児童福祉法」施行
- 「障害児通所支援」「障害児相談支援」創設
2016年「改正児童福祉法」施行
- すべての子どもは、福祉が等しく保証される「権利の主体」
2022年「こども基本法制定」制定
2023年「こども家庭庁」発足
児童福祉法に基づく障害福祉サービスの概要
2012年の児童福祉法改正により、障害児施設・事業が一元化され、市町村による障害児通所支援と都道府県による障害児入所支援の2種類に大別されています。なお、訪問系(居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、日中活動系(短期入所)については、障害児も障害者総合支援法による自立支援給付の対象となります。
障害児通所系
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
障害児入所系
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
奈良県 障害福祉サービスの指定申請
障害福祉事業で指定を受けるためには法人格が必要です。また、法人設立にあたって定款を作成しますが、定款の目的に指定を受ける事業を行うことが明記されている必要があります。その他、サービスの種類に応じて、人員配置や建物の設備要件もあります。
(1)事前相談
奈良県では、指定申請前に事前相談制度が設けられています。指定の「事前確認シートを作成の上、初回の事前相談期限である申請期限の2週間前までの開庁日までに、郵送で提出します。事前相談では以下の内容を含めて確認が行われます。(居宅系サービスは不要)
- 従業者等の資格、人員配置
- 事業に使用する建物の設備要件充足状況
- 他法令(建築基準法、消防法等)に基づき必要な手続きの進捗状況
- 事業概要・収支計画(就労系サービスのみ)
この段階で障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法、その他条例や事業内容に応じた関連法令等を確認して、要件を満たしているか、または申請までに満たすことが可能かをよくチェックしておく必要があります。
就労支援A型事業所では障害者の方を雇用するため新規指定を受けるためには以下のような要件も満たす必要があります。
・ 労働基準法に従い、就労する利用者に対して最低賃金以上の給与を支払うこと
・継続・安定的な事業収益が見込めること
・利用者に作業等を教えるための職業指導員や、利用者の生活支援を行う生活支援員の配置
・「専ら社会福祉事業を行う者」であること(社会福祉法人を除く)
(2)申請
指定を受けたい月の前々月の末日までに申請書と必要書類を提出します。
(3)受理(4)審査(5)指定
審査課程で問題がなければ指定通知書が発行されます。
奈良市 障害福祉サービスの指定申請
障害福祉サービスの指定申請は、事業所の所在地が奈良市の場合は、奈良市に、奈良市以外の場合は奈良県への申請となります。なお、児童福祉法における指定障害児入所施設等の指定申請は、事業所の所在地が奈良市の場合でも奈良県への申請となります。
奈良市では基準条例6条例に基づき指定障害福祉サービス事業者等の指定等を行っています。そのため奈良市への指定申請については最初に基準6条例と6条例に関する省令を確認する必要があります。
奈良市では事前相談を必須となっておりませんが、基準6条例及び各種法令に適合していない状態で申請した場合、一切受理されません。事前相談を行う際は、事前予約が必要です。
一部サービスについては総量規制があります。現在生活介護、就労継続支援B型については、令和9年3月31日まで、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供することを目的とした総量規制が行われています。ただし例外的な取り扱いの要件も併せて定められているので、該当事業であっても詳細を確認の上、申請可能な場合は、例外的な取り扱いを適用して指定を受けるための申請手順に従って申請をします。
(2)申請
指定を希望する月の前々月の末日を期限として申請を行います。期限を過ぎた申請や申請書類が不足している場合は受理されません。申請書の提出については完全予約制となっています。
(3)現地確認
審査の一環として、事業所・施設の現地確認があります(原則として訪問系サービスや相談を支援を除く)。
申請の手引きや基準等の自主点検表が奈良市より提供されています。また定款への記載にあたっての注意点等の情報も提供されています。事前に十分チェックをした上で手続きを進めることがポイントとなります。