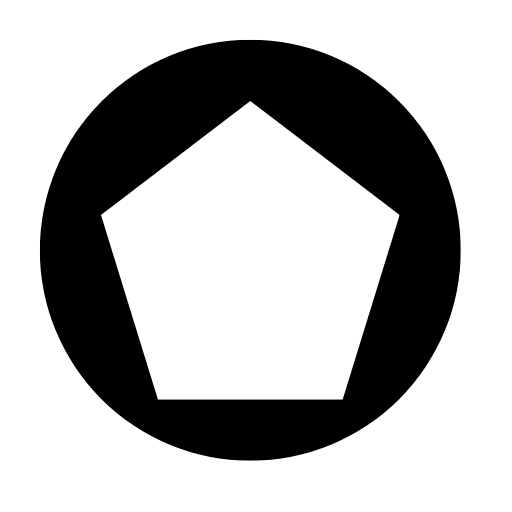保育所等訪問支援は放課後等デイサービスや児童発達支援同様に、指定障害児通所支援となることから、放課後等デイサービスや児童発達支援を単独型または多機能型で行なっている事業所にとって、新たに保育所等訪問支援を行うことは一つの選択肢となり得ます。その一方で、保育所等訪問支援は「障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう」支援を行うものとなりますので、障害児との集団生活における支援とは異なります。
対象
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認めれた障害児
人員基準
訪問支援員
訪問支援を行うために必要な数
なお、指定保育所等訪問支援の提供に当たる従事者の要件については、障害児支援に関する知識及び相当の知識を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者とする。
児童発達支援管理責任者
1人以上(専ら当該事業所の職務に従事する者であること)
管理者
原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(上記訪問支援員及び児童発達支援管理者を兼務する場合を除き、他の職務との兼務可
設備基準
専用の事務室が望ましい(他の事業と同一の事務室も可)
利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保する
その他、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品を備えること
保育所等訪問支援の内容
保育所等訪問支援では、支援の対象となるこどもを集団生活に合わせるのではなく、こどもの特性等に応じた集団生活の環境の調整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう進めていくことが必要です。そのため「障害のあるこども本人に対する支援」だけでなく、「訪問先施設の職員に対する支援」や「家族に対する支援」を通して、総合的に育ちの環境を整えていくことが重要です。
こども本人に対する支援
こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生活への適応や日常生活動作の支援を行います。
訪問先施設の職員に対する支援
訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させることができるよう、こどもの発達段階や特性の理解を促すとともに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や訪問先施設の環境について助言を行います。訪問先施設の意向を踏まえるとともに、訪問先施設の理念や支援方法を尊重する姿勢が重要です。
家族に対する支援
障害のあることもを育てる家族が安心して子育てを行うとともに、安心してこどもを保育所等に通わせることができるよう、保護者に対し、訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方を含め、提供した保育所等訪問支援の内容を伝えます。
訪問頻度
2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して支給決定されていますが、機械的に行うのでなく、個々の障害のあるこどもの状態に応じて柔軟に対応していく必要があります。
支援が進み、訪問先施設の環境整備や、職員や周囲のこどもたちの対応力が向上し、受け入れ状況が整ってきた際には、訪問の間隔を徐々に空けていくことが想定されています。
訪問時間
保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、こども本人に対する支援や訪問先施設の職員に対する支援、支援後のカンファレンス等におけるフィードバックを行うものであり、支援の提供時間については、保育所等訪問支援計画に定めた上で、30分以上とすることが求められています。
保育所等訪問支援計画の作成及び評価
保育所等訪問支援の適切な実施にあたっては、障害児相談支援事業所が、障害のあるこどもや保護者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わせについて検討し、障害児支援利用計画を作成します。その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、当該事業所が提供する具体的な支援内容等について検討し、保育所等訪問支援計画を作成し、これに基づく支援が提供されます。
障害児支援利用計画の作成の流れ
(1)障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定
(2)担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定
(3)保育所等訪問支援計画に基づく保育所等訪問支援の実施
(4)障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し
保育所等訪問支援計画の作成の流れ
(1)こども、保護者及び訪問先施設に対するアセスメント
事業所は保護者に対し、「5領域20項目の調査」の結果について確認の上、当該結果についてアセスメントをふうめ実際支援の場面にも活用していくことが重要です。
こどもの発達状況、自己理解、心理的課題、こどもの興味・関心、教育環境、これまで受けてきた支援、現在通っている保育所等や関わっている機関、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望について必要な情報を集め、こどもと保護者のニーズが課題を分析します。
こども本人のニーズ、保護者のニーズ、訪問先施設のニーズは必ずしも一致するものではないので、まずはこどものニーズを明確化していくとともに、三者のニーズをすり合わせていくことが求められます。
(2)保育所等訪問支援計画の作成
保育所等訪問支援計画の作成に係る個別支援会議の開催にあたっては、こどもの支援に関わる職員及び訪問先施設の職員を関与させることが必要です。
保育所等訪問支援計画には以下の内容を記載します。
- 利用児と家族の生活に対する意向
- 総合的な支援の方針
- 長期目標
- 短期目標
- 支援目標及び具体的な支援内容等
- 支援目標
- 支援内容
- 達成時期
- 担当者・提供機関
- 留意事項
事業所において作成した保育所等訪問支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付を行うことが必要です。
(3)支援の実施
- 訪問先施設との日程調整
- 行動観察
- こども本人に対する支援
- 訪問先施設の職員に対する支援
- カンファレンス(訪問先施設への報告等)
- 保護者への報告
- モニタリングに基づく保育所等訪問支援計画の見直し及び保育所等訪問支援の終結
関係機関との連携
- 保育所等(訪問の対象となる施設)との連携
- 市町村との連携
- 児童発達支援センターとの連携
- 児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所との連携
- こども家庭センターや児童相談所との連携
- (自立支援)協議会等への参加や地域との連携
- 保育所等訪問支援と類似する事業の実施機関との連携