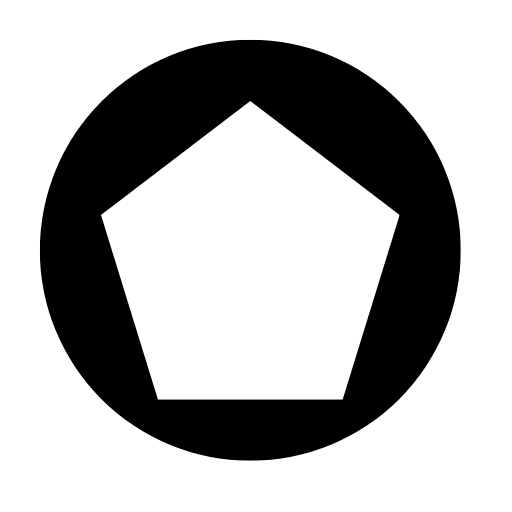法定を把握して、指定権者を知ること
障害者支援施設が満たすべき基準を満たさない限り、障害者支援施設の指定は受けられません。
障害支援施設には障害者総合支援法、児童福祉法に基づくサービスがありサービス事業ごとに、基準省令、人員・設備・運営基準、解釈通知があります。さらに基準省令から委任されている関係告示や、解釈通知の中で別に定めるとされた別の通知も存在しています。
そのため障害者支援施設の指定を受けるためには、対象サービスについて少なくともこれらの関連する法令等のすべてを把握して基準を満たす必要があります。
実際に指定を行うのは、指定権者となり、指定権者の多くは都道府県庁・政令指定都市ですが、地域によっては中核市等が指定権者となっている場合があります。いずれの場合でも、指定権者がどこになるかについて間違いなく把握することが必要となります。その上で、各指定権者の定める内容にしたがって指定申請の手続きを進めます。
法人であること
法人でないと指定を取ることができません。障害福祉施設では、NPO法人、一般社団法人、株式会社、合同会社のいずれの法人形態もあり、設立や運営を考慮して最適な法人形態が選ばれています。障害福祉施設に限った話ではありませんが、傾向として合同会社が増えていると言えます。合同会社は株式会社よりも設立費用が低く、運営もしやすいというメリットがあります。障害福祉施設の公的な性質上、NPO法人も多いです。NPO法人は設立のハードルが高いですが、税金面でのメリットがあります。障害福祉施設を必要とする方々は多く、そういった方々の要請と寄付を受けて、NPO法人として設立・運営されていることが多いです。あくまでイメージの問題となりますが、そういった公的な背景があるためNPO法人は社会的な信用を得やすいという側面もあります。
人員配置基準を満たすこと
サービス毎に定められた人員配置基準があります。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、生活支援員、職業支援員、医師、看護師などの必要な人員がそれぞれのサービス毎に定められており、実務経験、研修受講、資格等の要件が定められています。
常勤換算
人員基準を満たす上で、常勤換算という方法が用いられます。常勤換算方法とは、勤務延べ時間を勤務すべき時間数で割って1.0以上となれば常勤、1.0を下回ると非常勤となります。1週間に勤務すべき時間が32時間を下回る場合は、32時間を基本とします。例えば1日に勤務すべき時間が6時間、週5日勤務の場合は、1週間に勤務すべき時間が30時間となります。この場合においても32時間が基本となるので、30時間勤務したとしても1.0を下回ることになります。
専従
サービス提供の時間帯を通じて、他の障害福祉サービスに勤務しない場合は専従となります。サービス提供の時間帯で、他の職務に同時に従事する場合は兼務となります。
指定基準を満たすためには、常勤・非常勤と合わせて、専従・兼務を組み合わせた4パターンで勤務体制を整理する必要があります。
物件・設備の基準を満たすこと
日中活動系・就労系・居住系・通所系のサービスの場合、事業所は都市計画法、建築基準法、消防法、その他条例等にも適合する必要があります。
物件は申請前に確保する必要があるので、物件選びの段階から関連法令を把握して上で行う必要があります。
また、サービスごとに設備基準が設けられており、相談室、洗面所、便所、多目的室といった基準を満たす必要があります。
運営の基準を満たすこと
サービスの内容に応じて、内容及び手続きの説明、受給資格の確認、緊急時の対応、衛生管理など、様々な運営に関する基準が定められています。指定を申請するにあたっては、これらの運営の基準を満たす書類(運営規程、重要事項説明書、業務継続計画等)を整備しておく必要があります。